「野生のヒグマと初めて目が合った」出没に揺れる村の密着取材から感じた“駆除を批判する前にすべきこと”ドキュメンタリー映画『劇場版 クマと民主主義』幾島奈央監督
2025年03月27日(木) 13時32分 更新

鳥獣保護管理法の改正や、指定管理鳥獣への追加など、全国でクマ対策の大きな転換点を迎えています。
クマをめぐっては、特に「駆除」をめぐってさまざまな立場からの意見があり、ときには強い言葉がぶつかり合います。
私は北海道の放送局の記者として道内各地のクマ出没を取材し、ドキュメンタリー映画『劇場版クマと民主主義』を制作しました。取材の中で、私自身が「クマの駆除」についての考え方が変わる経験をしました。
冬眠明けの春を前に、北海道での取材から感じたことをお伝えします。(HBC北海道放送・幾島奈央)
■偶然取材を担当した、1頭のクマ
私は北海道の放送局・HBCに2018年に入社し、報道記者になりました。
配属2か月目のある日、上司から電話がかかってきました。
「島牧村っていうところにクマが出たから、行ってくれない?」
報道記者、特に新人は、事件事故が起きるとすぐに現場に向かいます。
私は特にクマにくわしかったわけでも関心があったわけでもなく、偶然、現場に行くよう指示されました。 北海道島牧村(2018年)
北海道島牧村(2018年)
その村で、初めて野生のヒグマに出会ったときの画像です。
クマはこちらを見ています。目が合いました。
野生のヒグマに出会った、そう聞くと、恐怖を感じるかと思います。
しかしこのとき、私は怖くありませんでした。
クマが顔を出したのは住宅のすぐ後ろの草やぶです。前足をかけているフェンスを乗り越えれば、すぐに住宅の庭に降りられる位置です。
クマと庭をはさんでハンター数名が向かい合い、警察が並び、その後ろに私たちメディアがいました。
ハンターがクマをライトで照らします。顔のまわりに白い模様が見えました。
「ああ、あいつだ」
ハンターの声で、数日前から出没を繰り返していたクマだとわかりました。
たくさんの人に見つめられながら、クマは、落ち着いていました。
その目に、人を襲おうとする様子は感じられませんでした。
じっとこちらの様子を見つめています。
「おお降りるぞ!」ハンターが声をあげます。 北海道島牧村(2018年)
北海道島牧村(2018年)
クマが体を乗り出してきました。
ハンターが爆竹を投げます。
バチバチッと大きな音が鳴り、クマは体を隠しました。 北海道島牧村(2018年)
北海道島牧村(2018年)
しかし、その目はまだこちらを見ています。
フェンスにかけた前足も降ろしません。住宅地に降りたいという、強い執着を感じました。
このとき私はただ、「早く山に帰ってくれたらいいのに」と思っていました。
小さな頃から動物が好きだった私は、「クマを殺すなんてかわいそう」と、正直、ハンターに悪い印象を持っていました。
札幌出身で、身近で出没情報があり集団下校をしたことなどもありましたが、それでも「人もクマも傷つかないのが一番いい」と思っていました。
目の前にクマがいるこのときでさえ、落ち着き払い、人を襲おうとする気配のないクマの様子に、怖いとはまったく感じませんでした。
ただ、怖いと思わないことの怖さを、この後学んでいくことになります。 北海道島牧村(2018年)
北海道島牧村(2018年)
住宅地には、クマの食べものになるものがありました。それにクマは引き寄せられていたのです。
その個人が悪いのではありません。長年の人間社会の習慣や、人口減少などの変化が積み重なり、数十年かけて、クマが出やすい環境ができてしまっていたのです。村だけでなく、全道・全国で起きていることです。
クマは本来、人を怖いと思っていて、住宅地には近づきたくありません。
しかし、一度住宅地でおいしい思いをしたクマは、繰り返し現れます。
そして住宅地に出ても人に攻撃されないことも学習します。
人に出会ってさえ、ただ見ているだけで攻撃はされない…そうして人に慣れていくのです。
人を怖いと思っているクマなら、クマ鈴の音などで先に気づいて逃げてくれます。
しかし慣れているクマは、ばったり人に出会うリスクが高まります。もともと襲うつもりはなくても、ばったり出会えば、とっさに身を守るために人を攻撃することもあります。
「かわいそう」「山に帰ってほしい」そう願いながらクマを見つめていた、無知な私も、クマの人慣れを進めてしまった、そして駆除しか選択肢がない状況へと導いてしまった、一因なのでしょう。
■「殺さないとダメ?」ハンターにぶつけた質問
私が学んでいくのは、専門家の取材などを重ねてから次第にです。
当初の私は、「殺さないとダメなのか」と思っていました。その思いを、直接ハンターに投げかけました。
最初はインタビューを嫌がるハンターもいましたが、答えてくれた一人はこう言っていました。
「住民の人らが怖がっているから」
本当にそれしか選択肢はないのか…まだモヤモヤした気持ちを抱えていた私は、村に残って取材を続けました。 入社1年目当時の筆者。柵の向こうは海で、海の岩の上にクマがいる
入社1年目当時の筆者。柵の向こうは海で、海の岩の上にクマがいる
クマは毎晩のように現れました。住宅の庭を荒らし、小屋を壊し、海を走り回りました。
最初は草やぶから顔を出して様子を伺っていたクマが、目の前を走り、歩き…次第に行動が変わっていくのがわかりました。
海の中にいたクマが、ハンターが立つ住宅地の方向へと突っ切って進もうとした場面もありました。ほかのハンターらが一斉に大声を出し、クマを追い返します。
現場の緊張感は増していました。
ハンターは村の要請を受けて、連日の追い払いにあたります。
クマはきょう現れるのか、何時にどこで現れるのか、わかりません。
ハンターたちは日中はそれぞれの仕事に行き、夕方に集合して、村中にしかけた罠の見回りをします。日が暮れるとそれぞれの持ち場について、車の中から山のほうを見つめます。
クマが現れれば無線で連絡を取りあって追い払い、日付を越えたころ、クマが山へ帰ってくれたら家に戻ります。その瞬間にまたクマが現れて、未明まで追い払いを続けます。
そして早朝、また罠の見回り。それから仕事へ向かい、また夕方に集合します。
■毎晩のように顔を合わせた、クマと人
毎晩のように、クマと顔を合わせました。
山のどこかにいる想像上のクマではなく、今、目の前にある命。「殺されるのはかわいそう」という気持ちは消えません。
しかし一度味を覚えたクマは、追い払っても追い払っても、また戻ってきてしまいました。
次第に、現実も見え始めていました。
同時に、村の人たちともたくさんの時間を過ごし、たくさんの話をしました。
夜はハンターの隣で、山を見つめる時間を過ごしました。
翌朝、疲弊したハンターの表情を見ました。それでも住民に「おつかれさん」と声をかけられると笑顔を返し、「住民が困っているから、なんとかがんばろう」と励まし合う姿を見ました。 北海道島牧村(2018年)
北海道島牧村(2018年)
日中は村を歩きました。「本当にこわい」「よく眠れない」と、たくさんの不安の声を聞きました。
そんな大変な日々なのに、私のことを気遣って「コーヒー飲んでいきな」と声をかけてくれたり、干している魚を突然「うまいぞ!持って帰れ!」と呼び止めてくれたり、あたたかい人柄を感じる瞬間が多くありました。
私が札幌に戻っている合間には「元気?また来てね」と手紙が届き、村の未婚男性を紹介してくれようとする人までいました。
この人たちに、クマとの事故で傷ついてほしくない。
クマに怯えずに過ごしてほしい。
その思いも、どんどん強くなりました。
■クマが駆除された日
2018年9月。胆振東部地震が起き、私は胆振の厚真町や札幌本社で過ごす時間が多くなっていました。
9月末、島牧村のハンターからの電話で、あのクマが罠に入ったことを知りました。
最初の出没から、ちょうど2か月。静かな村に、銃声が響きます。
もう一度、「駆除しか選択肢はなかったのか」と、ハンターに聞きました。
カメラの前で、こう話してくれました。
「できれば駆除はしたくない。でも、今回のようなクマになると人間を襲う可能性は確実に高いので…」
「北海道ヒグマ管理計画」では、今回のように生ごみなどを荒らし、繰り返し出没するクマは、「問題個体」として確実な駆除を奨めています。
ハンター個人の感情ではなく、クマの様子や経緯から、北海道の計画に沿って、自治体が判断するのです。
命のその後に向き合うのも、ハンターです。
「ただ殺すんじゃなくて、殺したら、それを食べる」「最初は抵抗があったけど、命をおいしくいただかないと」村のハンターは、クマを捕獲した後、その肉を鍋にして食べます。
丁寧に解体され、きれいに切られて、冷凍庫に保管されていた肉。
煮込む間に部屋中に立ち込める、獣の匂い。
鍋を囲むハンターたちの、噛みしめ、味わう表情。
命を感じる一瞬一瞬に、毎晩のように顔を合わせたあのクマの表情が浮かびました。
ハンターに悪い印象を持ちながらも、「かわいそう」と思うだけで何もしていなかった私は、人の命にも、クマの命にも向き合っていなかったのだと、気づかされました。
■駆除で終わり、ではない
食事の風景まで撮影させてくれるようになったハンターたちですが、駆除のニュースが出ることへの不安も口にしていました。依頼されて駆除する立場なのに、ハンター個人に批判が来ることもあるというのです。
最初のころ、取材を嫌がっていたハンターの表情を思い返しました。
話し合うことで、初めてわかる思いがあります。
何も知らずに批判することには、怖さがあります。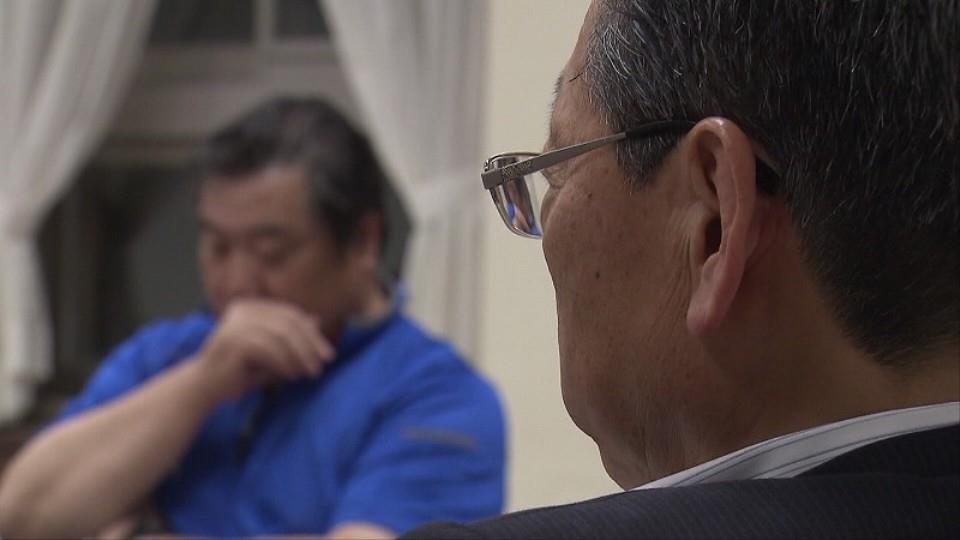 北海道島牧村(2019年)
北海道島牧村(2019年)
この騒動はクマの駆除では終わらず、政治の問題・民主主義の問題へと広がっていくのですが、その中でも住民や村の職員、村長、議員など、たくさんの方と話しました。たくさんのことを学びました。
率直な疑問を投げかける私に、向き合い、対話を重ねてくれた島牧村の人たちに、記者として・人として、育ててもらったと思っています。
全道各地のクマ出没を取材するようになり、人にできる対策も多く知りました。
「人もクマも傷つかないのが一番いい」という思いは変わっていませんが、だからこそ駆除を批判するのではなく、駆除しか選択肢がなくなる前に、すべき行動があるということを学びました。
放送局にいる立場で、まずはクマについての教訓や対策を伝え続けたいと、これまで7年、取材や発信を続けてきました。
クマ対策の草刈りなどに毎年参加し、対策や啓発のイベントを企画するようにもなりました。 札幌のクマ対策の草刈りで、等身大パネルを置いて効果を視覚化する実証実験を行った。見通しがよくなるとクマの侵入を防ぎ、ばったり出会うリスクも減らせる。白いTシャツの後ろ姿が筆者
札幌のクマ対策の草刈りで、等身大パネルを置いて効果を視覚化する実証実験を行った。見通しがよくなるとクマの侵入を防ぎ、ばったり出会うリスクも減らせる。白いTシャツの後ろ姿が筆者
ドキュメンタリー映画『劇場版 クマと民主主義』を制作したのも、その続きの取り組みです。
日々の短いニュースでは伝えきれないことを、一人でも多くの人に知っていただき、じぶんごとにして考えていただきたいと思っています。
クマ対策は一人では前に進められません。私の活動の影響力はほんのわずかでしょうが、「知っていれば防げた」はずの出没や被害が、ひとつでも減ることを願っています。
2019年、私は今度は札幌市内の住宅地で、野生のヒグマと出会うことになります。
そこで衝撃を受けたのは、「村の課題が繰り返されている」ということでした。【関連記事:後編へ続く】
文:北海道放送幾島奈央ドキュメンタリー映画『劇場版クマと民主主義』(東京で3月30日・札幌で4月5日~上映)を監督。
2018年に入社後、クマの取材を継続してきた。
2021年からWEBマガジン「Sitakke」の編集部


